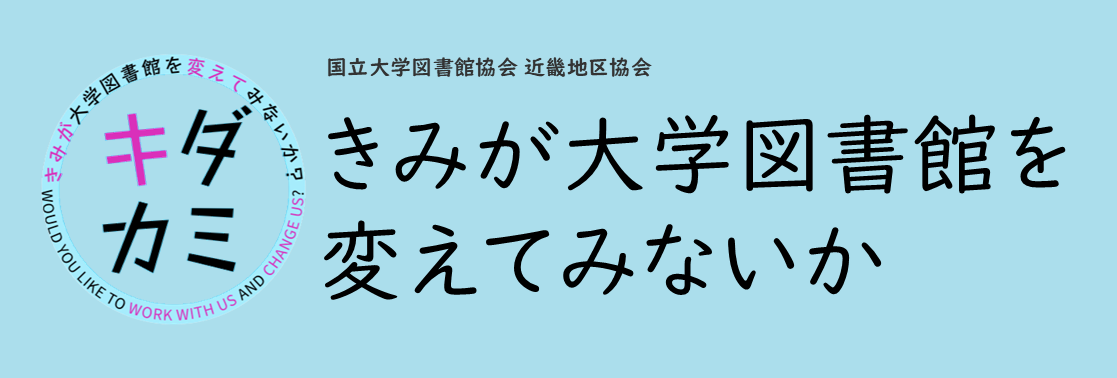大学図書館員が日々行っている様々な業務について、職員にインタビューした内容を紹介していきます。
今回インタビューに答えてくださったのは、
大阪大学附属図書館 図書館サービス課 情報ナビゲート班 学習・調査支援担当の坂田さんです。
レファレンス業務の大変さや面白さってどんなものがあるんでしょうか?
事前アンケートでいただいた回答(枠内)をもとに、キダカミメンバーの わにわに、猫部、みかんの3人がインタビューしてきましたよ!
坂田さん、教えてください!
※インタビュー実施日:2025.3.13
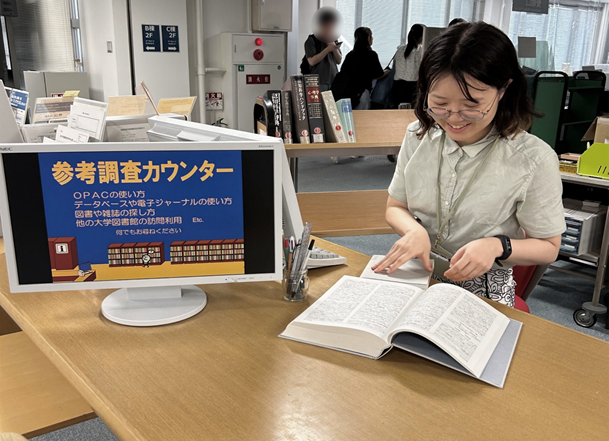
- Q1. 現在ご所属の図書館サービス課 情報ナビゲート班 学習・調査支援担当では、主にどんなお仕事をしていますか?
- Q2.働く前のイメージと実際のお仕事に違いはありましたか?
- Q3.いまのお仕事で、大変な部分と楽しい部分を教えてください!
- Q4.大変な部分は、どう乗り越えましたか?(あるいは乗り越えている途中ならどう頑張っていますか?)
- Q5.1日の簡単なスケジュールを教えてください!
- Q6.今のお仕事で、印象に残っていることはありますか?
- Q7.民間企業の営業職をされていたそうですね。その経験が現在の業務に活きていると感じる点があれば教えてください!
- Q8.ご担当の業務以外で、他部署や組織外の方と連携して進めているお仕事はありますか?もしあれば、どのような内容か教えてください!
- Q9.これからの展望(自分はもっとこうなりたいorこういうことに取り組んでいきたい)を教えてください!
- Q10.最後に、大学図書館を志望する方々にメッセージをお願いします!
Q1. 現在ご所属の図書館サービス課 情報ナビゲート班 学習・調査支援担当では、主にどんなお仕事をしていますか?
学習支援では、大学院生のラーニング・サポーター(LS)による学習支援の実施、図書館での講習会および授業やe-learningによる情報リテラシー教育を、調査支援ではレファレンスサービスを担当しています。
―― 学習支援と調査支援の対象は、全分野ですか?(み)
坂田:
基本的に、カウンターに来られた方の質問には、どの分野であれお答えはしています。現在私がレファレンスカウンター職員として出ている図書館が豊中キャンパスにあり、理工系の学部の方、特に1年次生の方も利用されるのですが、数学に関する質問が時々あるかな?というくらいで、理系の質問はあまり受け付けることがありませんね。ただ、医学系の文献検索になるとちょっと対応が難しいことがありますので、そういう時には、吹田キャンパスの生命科学図書館が医学系図書館ですので、そちらの担当者の方と連絡を取って、引き取ってもらったりしています。
―― 他の館にも同じような係があるのですか?(み)
坂田:
そうですね。ほかのキャンパスの図書館にも利用支援担当の部門があって、利用支援担当の方々が閲覧もレファレンスもやっている形です。総合図書館だけちょっと規模が大きいので、その閲覧とレファレンス学習支援が分かれて、別の係でやっています。
―― そうなんですね。LSさんがいるというのが羨ましいです。(み)
坂田:
本当に助かっています。やっぱり授業はがっつり一年生から数学や物理、化学の課題などがありましてですね。私たち職員は、あくまでレファレンスなので、そういう「授業で出た課題が解けない」等のご相談には対応できないんですけれども、代わりに、大学院生のスタッフであるLSさんに来ていただいて、私たち職員の横に授業期間中座っていただいていてですね、そういう学生さんが来たら、パッと相談に乗ってあげたりしてもらえています。なので、LSさんの存在によって、そういう(図書館ができる)サポートの幅が広がる、広がるのがすごく嬉しい、ありがたいっていうのを私自身も思っています。もう一つありがたいのが、「今の院生さんがどんな生活を送っているんだろう」とか、普段の時間の使い方とか、あるいは「どのように論文を検索や保存しているのか」とか、そういうのをパッと聞けるのが、(LSさんは)職員でありユーザーでもあるので、そのユーザーであるところも私はとても頼もしく思っています。

Q2.働く前のイメージと実際のお仕事に違いはありましたか?
学生時代に司書課程を履修しており、調査支援は予想範囲内でした。一方でアカデミック・スキルについて自分が人に教える側に立つとは思ってもみませんでした。
―― 坂田さんも司書課程を履修されていたから、レファレンス自体の想定は…(わ)
坂田:
はい、想定はしていて実習もありましたので、レファレンスをすることもあるかもなと思っていました。まさかこの担当になるとは思っていなかったので、嬉しいなあと思っていたんですけど。学習支援っていうところで、文献の検索方法や入手方法を説明するにあたって、それだけ切り出すんじゃなくて、前後の文脈で、『レポートを書きましょう』、で『書くにはやっぱり、まずは調査が必要ですよね』っていう説明もしてから、その文献の調べ方や入手の方法などを説明していくので、やっぱりレポートの書き方についても勉強というかおさらいというかをしなくてはいけなくて。しかも自分でおさらいするだけじゃなくて、「このようにやりますよね」って教える立場になるっていうのが、そこまで踏み込むんだっていう、すごく責任というか、重みを感じてちょっと最初は慣れなかったです。
Q3.いまのお仕事で、大変な部分と楽しい部分を教えてください!
楽しい部分:利用者さんやLSさんとお話しする機会が多いです。
大変な部分:利用者さんを取り巻く情報環境等の動向を追い続ける必要があります。
Q4.大変な部分は、どう乗り越えましたか?(あるいは乗り越えている途中ならどう頑張っていますか?)
(今のお仕事に限らず)利用者の置かれた環境の把握とサービスの改善は終わりなき課題でありやりがいなのかも。最近特に注目しているのは生成AIツールです。
―― 高校までに学生がどこまで調べものをしてきたかについて、個人差を感じたりとかは…(み)
坂田:
そうなんです。実はうちの担当ではないんですけど、うちの図書館の職員が大学職員向けの職員研修を企画されて。そこで高大接続の先生がおっしゃっていたんですけども、高校によって、「探求の時間」がある / ない、またはあってもがっつり指導するか、それとも「総合的な学習の時間+α」ぐらいでされているかなど、結構バラバラだそうです。その先生は「レディネス」っておっしゃっていたんですけど、「大学の学びに対して準備がどれだけできているか」がかなり多様化しているので、受け入れる側も様々なレベルの方に対応しなきゃいけないのかなという話をされていました。
―― LS さんがいるというのは、そういう「高校でどれくらい調べものやった?」などの会話もできるんだろうなと思うと、本当に羨ましいなと思いますね。(み)
坂田:
確かに高校の時、どんな感じだったとか聞きますね。聞きます!笑
Q5.1日の簡単なスケジュールを教えてください!
毎日3~4時間はレファレンスカウンターに出ています。残りの時間は事務室にいて、時間のかかる調査や訪問利用のアレンジ、教材の更新、WG業務などを行っています。
―― もちろん時期にもよると思うんですけど、1日何人ぐらいカウンター来られますか?(猫)
坂田:
全く来られないっていうことはなくて。でも今月みたいな凪の月だとだいぶ少ないですね。お2人とか3人。それぐらいですね。なのでカウンターに行っても結局事務室内でやるようなことをやっていることも結構多いです。
―― どんな感じの質問が多いですか?「この資料が見つからないんですけど」っていうのもあれば、「こういうのを調べたくて、何かそれに役立つ資料を探してください」というがっつりしたものまで幅があると思うんですけど。(猫)
坂田:
おっしゃった中では、がっつりしたものは本当に少ないです。ひと月にあるかないかぐらいかなって思います。多いのは「この論文とか探しているけども、探し方がわからない」とか、「阪大では持っているはずなのになぜか読めない」とか。購読の期間から外れていることが多いですね。
あともうレファレンスでは厳密にはないんですけど、そのレファレンスカウンターの横にプリンターがあるので、「プリンターの操作がわからない」とか。それからそのカウンターの奥にお手洗いあるんですけど、「お手洗いどこですか」とか。数としては、実はそういう方が多いですね。
―― レファレンスカウンターとは別に、貸出返却のカウンターがあるんですか?(猫)
坂田:
あります。玄関入ってすぐのところにメインカウンターっていうのがありまして、そちらでもやっています。
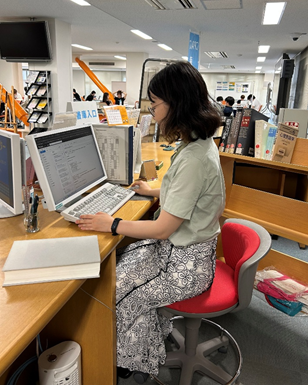
Q6.今のお仕事で、印象に残っていることはありますか?
教員の文献探索を何回かサポートしたところ、後日論文公開のご報告をいただきました。発見・入手のお手伝いをした文献が参考文献リストに並び、嬉しかったです。
―― これは羨ましい。(わ)
坂田:
これはもう僥倖ですね。しかもおまけがありまして、この論文がうちの機関リポジトリにのっていて、そこも嬉しかったです。
―― この”何回かサポート”っていうのはやっぱりカウンターのパワーかなっていうふうに思って、いいなと思いました。(み)
坂田:
うん、確かに「特に相談はないけど、来ました」みたいな感じでお声かけしてくださるようになって。
―― やっぱりカウンターに座っていて、「あ、誰々先生だ」みたいなのがありますか。(み)
坂田:
いらっしゃいます。今の部署ならではかなって思いますね。ちょっと問3(いまの仕事で楽しい部分)とも関連してくるかもしれないんですけども、たくさんの利用者さんのお名前と顔が一致することもあります。
Q7.民間企業の営業職をされていたそうですね。その経験が現在の業務に活きていると感じる点があれば教えてください!
会話の中で面談者の課題を明確化していく経験や、情報をどのような順番や切り口で提示すれば伝わりやすいかというノウハウは、今の業務にも活きているなと感じます。
坂田:
私は前の職場では営業職だったんですけれど、ルート営業といって、決まったお客さんに商談をするということをしていました。飛び込みと違って、ある程度時間がかかってもいいから、信頼関係を築いて。話しながら、どんなことで困ってはるのかっていうのを受けて、「それであれば、うちで持っているリソースでこんなふうに解決できます」っていう流れで話していくんですけど、それが今のレファレンスでもそのまま応用できるなっていう場面が多くて。「こういうことができます」ってお伝えする時にも、やっぱりその方が持ってらっしゃる情報量であったり、いろいろな背景があるので、どういう順番や情報量、切り口でお伝えしたら伝わるのだろうかっていうのは考えながら話したりしています。
―― 私もこのお答えを見て、「おお、まさしくレファレンスインタビューだな」と思いました。坂田さん、広報物を作る時にすごくきれいにデザインしていらして。(わ)
坂田:
ありがとうございます。
―― 以前、一緒に広報の仕事させていただいていたんですけど、その時すごくきれいにレイアウトなど考えてくださって、「ああ、違う業界の経験って、こういうところでとてもありがたいな」と思いました。(わ)
坂田:
一応、広告を売る会社にいて、私は制作には全然携わってなかったんですけど、制作さんと一緒に営業同行して提案することはあって。「そういうところ、気にしてはりながら作るんやなあ」っていうのも、見ながらやってました。
Q8.ご担当の業務以外で、他部署や組織外の方と連携して進めているお仕事はありますか?もしあれば、どのような内容か教えてください!
総合図書館で購入する学習用図書の選書や、附属図書館の5年間の将来構想検討に関わっています。国立大学図書館協会資料委員会の企画として公開勉強会を企画することもありました。
坂田:
係以外の仕事が年を重ねるごとに増えてきたと思います。それは職歴が増してきたからなのか、それともそもそも図書館が他の機関の方々と共同で話し合ったり、何か物を作ったりしていかないと難しい時代になってきたということなのか、どちらかなのかは分からないんですけど。でもまあ、そういうチャンスがもらえる職場だなと思います。
―― 私も一年目ですけど、いろいろ顔を出させてもらってて、それこそ海外行かせてもらうなど、むしろ係以外の仕事の方が多いんちゃうかっていうぐらいで。いろいろチャンスがもらえる職場だと思います。(猫)
坂田:
キダカミは京阪神のその横のつながりっていうところで、そういうところに一年目から入られているっていうのがすごいです。
―― まあ、僕も新人っていうか、一応新人は新人ですけれど、転職組で職歴が四年ぐらいありまして。でも一年目でもやっている人はいろいろいると思うんで、チャンスがもらえる職場だと私も思います。(猫)
坂田:
裏付けていただきました。笑
Q9.これからの展望(自分はもっとこうなりたいorこういうことに取り組んでいきたい)を教えてください!
蔵書構築や目録整備についての理解を深める。学生・教職員が学習・研究に必要な情報を思うままに入手できる環境を目指し、他担当・館外・学外の関係者各位と協働する。
坂田:
一文目と二文目で全然違うこと書いているんですけど。図書館に来て、利用支援系の仕事をやる前は、機関リポジトリの仕事をやっていたんです。図書館のこのコアになる部分、情報資源の整備とかコレクション構築とか、そういうところ全くタッチしてないまま、結構年数を重ねていまして。でも、図書館の価値の根幹って割とこういうところにある気がする。これが整っているから、私はこれと利用者をつなぐ仕事をできるんですよ。利用者さんが困っていても、コレクションや目録がないと、私は何もできないんですよ。だからやっぱりカウンターに出て、仕事しているうちにもっと目録のデータの構造のこととか、コレクション構築の方針とかについて理解が深まっていれば、もっと利用者さんへの対応としても何かあるんだろうなっていうのがありました。そしてここから二文目なんですけれども、そのサービスの質を向上していくっていうところで、やっぱり今、学生さんとか教職員の方がかなり学習研究されている環境が変わってきている。AI が出てきたっていうのもありますし、あと阪大では、研究も学習もハイブリッドでやれるようにしてかなきゃねっていう、大学として方針が決まっているんですね。っていうときに、やっぱりちょっと今の既存の体制のままではなかなかしんどい。それこそ京阪神のデジタルライブラリーだったりとか、あるいは出版社の方やベンダーの方々と検討したり、話し合いをしたりしながら、うちの学生さんや教職員の方が必要な情報を必要な時にパッと入手できるような環境っていうのを作っていかなきゃいけないなと思っています。それで、他業種や他館の方とお話をするときに、自分のとこではこうやっていますっていうのをしっかり言えなきゃダメだなっていうのを思って。今まで実際そういう場面で、「私のことは説明したけど、じゃあ図書館の方ではどんなことをしているの?」と聞かれたり、あるいは、海外の大学図書館に行くことがあって、そこでも「うちの国ではこういうふうにやっているけど、じゃあ日本はどうなの?」と聞かれたり。そこで自分のことを言えないと、なかなかこう相互理解とかコミュニケーションとか進まないんですよ。
ということがあったので、まずは図書館がどういうことをやっているのかっていうのをちゃんと理解して、その上でその阪大の図書館の外、他者って言ったらすごく素っ気ない言い方になっちゃいますけど、そういう方と一緒に話し合って、それをサービスに還元していきたいという気持ちがあります。
―― 図書館のほかの部署とかとの関わりって、やっぱり結構難しいけれど、すごく大事やなって、僕も海外行って帰ってきてすごく思います。海外の方が全学的にという感じが強いように思いました。(猫)
坂田:
なるほど。海外のどのようなジャンルの…オープンアクセスですか?
―― はい。坂田さんが海外に行かれた時のテーマは…(猫)
坂田:
これも実はその、リポジトリ担当時代に行ったので、やっぱり研究支援、特にオープンアクセス研究成果のオープンアクセス化支援でした。オーストラリアに行って、研究成果のオープンアクセス化の方針の調査とか。四つほど大学を回って図書館の方とお話ししました。面白かったですね。図書館に行くんですけど、URA1の方、事務の方と3人で行ったので、「ああそういうふうに図書館のサービスを見るのか」とかですね。同行しているチームの中でも面白い話がありました。
―― 阪大の図書館にはURAの方はいらっしゃらないんですけど、研究開発室の先生はいらっしゃいますよね。URA は阪大の場合は吹田の本部の方に部局があって、 URAの方にお会いしたことがないので、どんなことしているんだろう?って。阪大全学に毎年1回募集がかかりますよね、URAって。(わ)
坂田:
そうですね。今は事務職員から URA を目指してみない?という学内リクルートが始まっていて、部長はどんどん行きなさいっておっしゃっていましたね。
- URA…”University Research Administrator”の略称。大学等において、研究者とともに(専ら研究を行う職とは別の位置づけとして)研究活動の企画・マネジメント、研究成果活用促進を行う(単に研究に係る行政手続きを行うという意味ではない。)ことにより、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材を指します。
【出典】文部科学省 大学研究力強化委員会(第9回)令和4(2022)年11月2日(水)資料6より ↩︎
Q10.最後に、大学図書館を志望する方々にメッセージをお願いします!
受け身に思える「サポート」という役割が、その実とてもクリエイティブな行いであることを実感する日々です。転換期にある図書館でお知恵やご経験を活かしてください!
今回のインタビューはここまで!
坂田さん、大変お忙しいところ、インタビューのためのお時間をいただき、ありがとうございました!