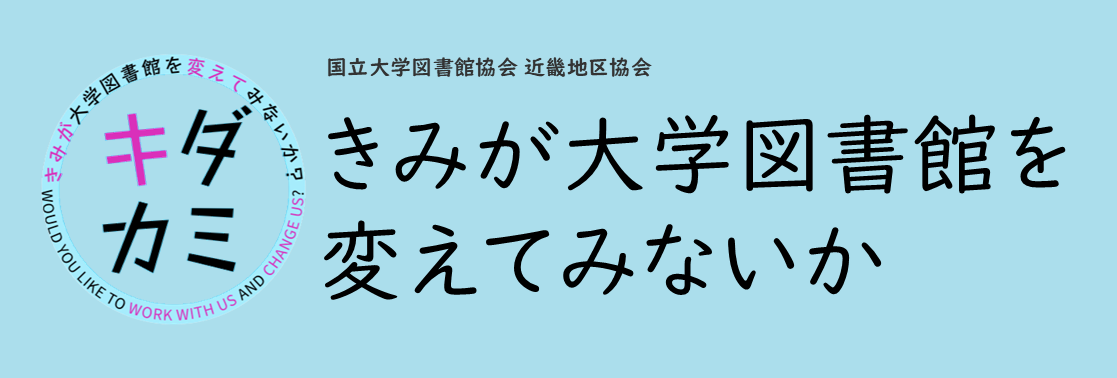概要
- 主催:国立大学図書館協会近畿地区協会助成事業 「きみが大学図書館を変えてみないか」(通称「キダカミ」)
- 実施日:2025年1月24日(金) 14:00~16:00
- 実施方法:オンライン(トークセッション会場:大阪大学総合図書館 図書館ホール)
- テーマ:新しい大学図書館員としてのスキルとキャリア
- 対象:国立大学図書館協会近畿地区協会会員館に所属する主任・係員級の職員
- 登壇者(敬称略):
- トークセッション第一部「エグゼクティブの軌跡と期待」
- 小陳左和子(大阪大学附属図書館 事務部長 入職37年目)
- 赤澤久弥(京都大学附属図書館 利用支援課長 入職29年目)
- 北條風行(神戸大学附属図書館 情報サービス課長 入職20年目)
- トークセッション第二部「ミドルマネージャーの働き方」
- 安原通代(京都大学附属図書館 研究支援課研究支援第三掛長 入職17年目)
- 藤江雄太郎(大阪大学附属図書館 図書館サービス課生命科学図書館班 管理主担当 専門職員 入職16年目)
- 花崎佳代子(神戸大学附属図書館 情報管理課電子情報グループ情報システム担当 専門職員 入職21年目)
- トークセッション第一部「エグゼクティブの軌跡と期待」
「大学図書館員としてのキャリアやスキルについて、不安を感じたことはありませんか?」
近年、大学図書館を取り巻く環境は大きく変化しています。デジタル化の進展、利用者ニーズの多様化、大学全体の変革が進む中で、図書館員の役割も進化が求められています。こうした状況の中、「新しい大学図書館員としてのスキルとキャリア」をテーマに、京都大学・大阪大学・神戸大学の附属図書館の現役管理職・現場職員が、主任・係員級職員に向けて自身の経験を共有するトークセッションが開催されました。
本レポートではその様子の一部をお届けします!
トークセッション第一部:エグゼクティブの軌跡と期待
大学図書館というフィールドでキャリアを築くなかで、出向や異動といった選択肢はどのように活かせるのか。また、大学図書館の未来をより良いものにするために、私たちは何を変え、何を守っていくべきなのか。本セッションでは、実際に出向も経験した経験豊富なエグゼクティブ層の登壇者たちがそのリアルな実態を語るとともに、大学図書館の現状と今後の展望について熱い議論を交わしました。
組織の枠を超えたキャリア形成のヒント、そして変革に向けた意識と行動の重要性。大学図書館に関わるすべての人にとって示唆に富むトークが展開されました。

①出向のリアル―希望を叶えるには?
大学図書館員のキャリア形成においては「出向」も選択肢の一つですが、異動先はどのように決まるのでしょうか?実際に出向経験のある登壇者が、その仕組みや希望の叶え方について語りました。
小陳(大阪大学):
「人事交流先については、完全に固定されてるわけではないんですけど、実際は調整が結構難しいんですよね。 例えば、こちらとしては係員級の人に行ってもらいたいと思っていても、相手側が『今は係長級がほしい』となったり。逆に『この人はキャリア的に適任だ』と思っても、その方の家庭の事情やライフイベントで今は異動が難しい、なんてこともよくあります。 さらに、給与などの処遇面で本人の不利益にならないような調整が必要な場合もあります。」
「こういう話って、若い方が聞く機会はあまりないかもしれませんが、大学の定員管理が厳しい中で、いろんな調整が必要になってくるんですよね。 とはいえ、管理職としては皆さんに色々な経験をしてほしいし、希望もできるだけ叶えられるようにと思っているので、やっぱり一番大事なのは”まずは自分の希望をしっかり管理職に伝えること”だと思います。 それから、信頼できる相談相手を持っておくのも大事ですね。」
「私自身、昔、上司に希望を伝えたんですけど、『それだけじゃ足りないかも?』と思って、他大学の人にも相談してみたんです。そうしたら、それが巡り巡って異動につながった、なんてこともありました。 ただし、こういう場合でも、事前に上司にはちゃんと伝えておかないと、話がこじれてしまうこともあるので、そこは気をつけるべきですね。」
普段なかなか知ることのできない出向のリアルな裏側が語られた本セッション。希望を叶えるには、まずは管理職にしっかり意思を伝え、信頼できる人脈を築いておくことが重要です。
②大学図書館はどう変わるべきか?―守るべきもの、変えるべきもの
今回の懇話会を主催する「キダカミ」のテーマである「きみが大学図書館を変えてみないか」に関連し、登壇者たちは「大学図書館界において変えてほしいこと、変えたいこと」「逆に変わらないでほしいこと、変えたくないこと」について、それぞれの考えを語りました。
北條(神戸大学):
「”変わってほしいこと”についてですが、”チャレンジする姿勢”ですね。大学図書館全体として、『何かやらなきゃいけない』と思ってはいるけれど、どこかで”誰かがやるのを待っている”ような空気を感じることがあります。で、『誰かが成功したら、それをちょっと真似してみようかな』みたいな。でも、そうじゃなくて、もっとみんながどんどんチャレンジして、新しい事例を増やしていく。そうすれば、その中から本当に良いものが自然と見つかっていくし、大学図書館界全体がもっとスピード感を持って動けるんじゃないかと思います。」
変わらないでほしいことについては、意外にも「特にないですね(笑)」と即答した北條課長。図書館のあり方そのものも、変わるべき時には柔軟に変えていくべきだという考えを示しました。
赤澤(京都大学):
「昨日まで北米の大学図書館へ出張していたのですが、海外の図書館の人たちと話していて感じるのは、誰もがすごくアクティブで、自分たちで変えていこうとしている ということです。もちろん、国や予算の規模、大学の性格が違うので単純に比べることはできませんが、根本的に『変えていくのは自分たちだ』という意識を持っているんですよね。それって、”エグゼクティブが決めること”じゃないんです。それぞれのポジションでできることがたくさんあるはずです。よく『上がダメだから変えられない』って思いがちなんですけど、それって結局、同じ言い訳をし続けているだけなんじゃないかと。だからこそ、変えていくのは自分たちだという意識を持つことが大事 なんじゃないかと思っています。あと、”変わらないでほしいこと”をあえて挙げるなら…やっぱり、大学図書館が”学術情報の流通を支える”というバックグラウンドを持ち続けることですね。そこがなくなったら、もう図書館の存在意義が分からなくなっちゃうので。」
小陳(大阪大学):
「”変えたほうがいいこと”についてですが…”図書館の論理で考えすぎていること” でしょうか。いわゆる”白馬の王子様論争”という話があるんです。つまり、図書館員って、『図書館は良いことをしているんだから、白馬の王子様が守ってくれるはず』ってつい思ってしまうんですよね。『きっと予算をつけてくれるはず』『きっと誰かが助けてくれるはず』って。でも、現実はそうじゃない。『図書館は大事だから守られて当然』と思っているのは図書館の中の人だけかもしれないんです。だからこそ、もっとアピールしないといけない。例えば、”お城にガラスの靴を落としてでも、誰かに気づいてもらう”くらいのことをしないと、誰も助けてくれないんじゃないかと。で、『変わらないでほしいこと』をあえてひねり出すなら…”愛”ですかね。やっぱり、図書館で働く人って、自分の仕事に愛を持っていると思うんです。ただし、その愛が自己中心的なものにならないようにすることも大事です。”図書館のための図書館”にならないように、正しく愛を持ち続けること。それが、変わらないでほしい部分かなと思います。」
大学図書館の未来は、待っているだけでは変わらない。変えていくのは私たち自身であり、そのためには一人ひとりの意識改革と行動が求められているというメッセージが伝わるトークセッションでした。経験豊富なお三方の愛のあるメッセージに勇気付けられた参加者も多いのではないでしょうか。
トークセッション第二部:ミドルマネージャーの働き方
大学図書館の現場を支えるミドルマネージャーたちは、どのように職員と関わり、組織をより良くしていくのか。本セッションでは、職員のモチベーションを高めるための工夫や、図書館の未来を見据えた柔軟な運営のあり方について、登壇者たちが自身の経験を交えながら語りました。
職員との信頼関係の築き方、変化を前向きに受け入れる姿勢、そして大学図書館の価値をどのように社会に伝えていくか――日々の業務に直結するリアルな視点が次々と展開され、参加者にとって多くの学びと気づきをもたらすセッションとなりました。

①職員のモチベーションを高めるには?―信頼関係を築くためにできること
職員のモチベーションを維持し、前向きに仕事に取り組んでもらうために、ミドルマネージャーとしてどんなことを意識しているのか。登壇者たちは、それぞれの経験をもとに、職員との関わり方や環境づくりの工夫を語りました。
花崎(神戸大学):
「ちゃんとできているかは分かりませんが、まずは『ありがとう』をしっかり伝えることを心がけています。特に、大変な仕事をやってくれたときには、感謝の気持ちを伝えたり、ちゃんと褒めることも大切だと思っています。ただ、スキルの高い人がきちんと評価される環境がないと、モチベーションを維持するのって難しいですよね。個人の努力だけでは限界があるので、得意なことを活かせる場を作って、それが適正に評価される仕組みが整えば、もっとやりがいを感じてもらえるんじゃないかと思います。」
藤江(大阪大学):
「何か頑張ってもらったら、しっかりお礼を伝えるのはもちろんですが、それに加えて、新しい提案や気づきを出してくれたときに、できるだけ前向きに受け止めるようにしています。たとえば、『面白そうですね』『確かにそうですね』といった感じで、ポジティブな反応をすることで、意見を出しやすくなるんじゃないかと思っています。
もちろん、すぐに実現できないこともありますが、まずはしっかり話を聞くことが大事ですよね。相談しやすい雰囲気ができると、結果的に『自分の意見もちゃんと聞いてもらえるんだ』と感じてもらえて、仕事へのモチベーションアップにもつながるんじゃないかなと思います。」
安原(京都大学):
「私は、”何かあったらすぐに相談できる人”でありたいと思っています。困ったときに『この人なら一緒に考えてくれる』と思ってもらえるようにしたいんですよね。
『この人に聞けば正解が出る』というよりも、『一緒に悩んでくれる』『一緒に考えてくれる』という存在になれたらいいなと思っています。」
また、上司の立場でも、職員に相談を持ちかけることで関係が深まるという意見もありました。
藤江(大阪大学):
「こちらから係の人に『これ、どうしたらいいかな?』って相談することはありますか?」
安原(京都大学):
「めちゃくちゃありますね(笑)。たとえば、『こんな質問が来たんだけど、どうしよう?』とか、『この対応でいいのかな?』といった感じで、よく相談しています。
『一緒に考えてください』ってスタンスで話すことが多いですね。」
藤江(大阪大学):
「それ、すごくいいですね。自分が係員だった頃を思い返すと、係長から相談されると、『頼りにされてるんだな』って嬉しかった記憶があります。
人によるとは思いますが、上司に相談されることも、実はモチベーションアップにつながることがあるのかもしれませんね。」
②現場に近い私たちはこう感じる。―大学図書館の変えたいこと、変えたくないこと
藤江(大阪大学):
「最近は減ってきていると思いますが、『図書館のルールだからこうです』といった、杓子定規な対応がまだ残っているように感じます。
大学図書館の価値が問われている時代だからこそ、利用者一人ひとりとの信頼関係を築いていくことが重要になってくるのではないでしょうか。意見や問い合わせがあったときには、そのルールの背景や意図をきちんと説明したり、今後の改善の余地を検討したり、丁寧な対応を現場で積み重ねていくことが大切だと思っています。」
安原(京都大学):
「図書館業界は、私が採用された頃と比べても大きく変わりました。例えば、オープンサイエンスや研究データといった概念は、当時はまったく知りませんでした。
でも、新しいことを学ぶのって、本来すごく楽しいことなんですよね。『また覚えることが増えた…』とネガティブに捉えるのではなく、『こういう考え方があるんだ、学んでみよう』と前向きに受け入れることが大切だと思っています。
仕事をしながら、学び続けられる環境があるのは、この仕事の良さでもありますよね。」
花崎(神戸大学):
「大学図書館以外の人との交流は大事だと思っています。育児中に『大学図書館って何をしているところ?』という話題になったとき、一般的には『本を貸している場所でしょ?』という印象しか持たれていないことに気づいて…。本当に役立つサービス提供につながるよう、大学内外を含め、大学図書館外の方と関わる機会をもっと増やしたいと思っています。」「大学図書館員って、『自分の仕事を通じて社会に貢献したい』という想いを持っている人が多いと感じています。この『社会に貢献したい』という想いは、今後も変わらずに持ち続けられるといいなと思います。」
③ミドルマネージャーメンバーから参加者へのメッセージ
最後に、トークセッション第二部の登壇者から参加者の皆さんへメッセージが送られました。
安原(京都大学):
「私自身、出向や海外研修の打診があったときに、最初は『なぜ自分が?』と思いましたが、『でもちょっと面白そうかも』と挑戦してきました。これからも、そういう場面に出会うことがあると思います。『違う、そうじゃない!』と最初は思っても、『でもちょっと面白いかも』と少しでも感じたら、ぜひ飛び込んでみてください!」
藤江(大阪大学):
「今日こうした場に参加された皆さんは、きっと先輩や上司の話を聞いてみたいという思いがあって来られたんですよね。
ぜひ、身近な先輩や上司にも気軽に質問してみてください。遠慮せず、いろんな人に話を聞くことで、新しい気づきがあるはずです。」
花崎(神戸大学):
「私からは2つ伝えたいことがあります。1つ目は、失敗も含めてすべての経験が次につながるので、チャンスがあれば『難しそう』と思っても挑戦してほしいということ。
2つ目は、上司や周囲の人に相談することの大切さです。1人で悩まずに、『こういう状況なのでこうしたい』と明確に伝えれば、必ず誰かが力になってくれるはず。前向きに業務に取り組んでください!」
まとめ
トークセッション終了後は数名の小さなグループに分かれて、それぞれ参加者同士で業務や働き方の不安、悩み、 希望等の意見交換会と1分間の発表を行いました。意見交換会全体を通して小陳部長から以下のようにコメントをいただきました。
小陳(大阪大学):
「自分が若い頃に何を考えていたかは、正直あまり覚えていませんが、皆さんのお話を聞いて、いろんな迷いや不安を抱えているのだろうなと感じました。
でも、それはごく自然なことです。我々だって日々悩むことはありますし、大切なのは、話を聞いてくれる先輩や、悩みを共有できる仲間を持つことです。組織の枠を超えて、ぜひそうした関係を築いてください。
変化を促すには、皆さんが声を上げることも大事です。大学の人事制度や勤務形態も徐々に変わってきていますので、これから良い方向に進んでいくことを願っています。」

図書館の未来は、私たち自身の手でつくるもの。
今回の懇話会で語られた言葉が、現職の皆さんや将来大学図書館で働くかもしれない皆さんのこれからのキャリアにとって、何かのヒントになれば嬉しいです!