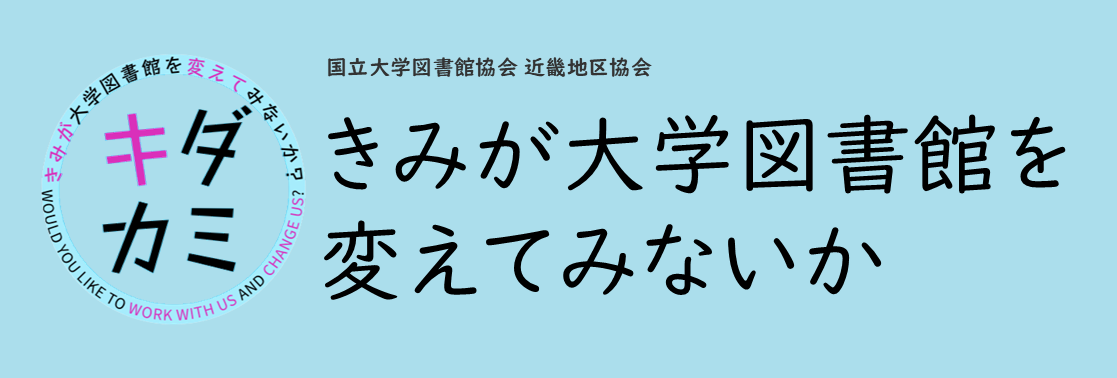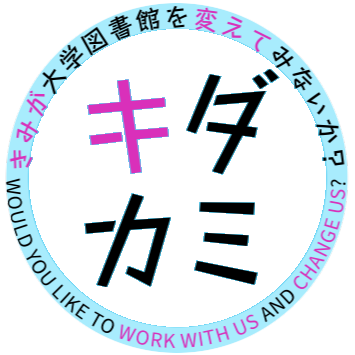普段、職員がどんなことを感じながら勤務しているのか、採用試験にどう取り組んだらいいのか。
大学図書館への就職を考えているみなさんの疑問に答えるべく、入職1年目の現役職員による座談会を実施しました。
志望動機や職場の雰囲気、試験対策まで本音で語り合ってもらいましたよ。
概要
- 実施日:2025年3月17日(月)
- 実施方法:オンライン
- 参加者:
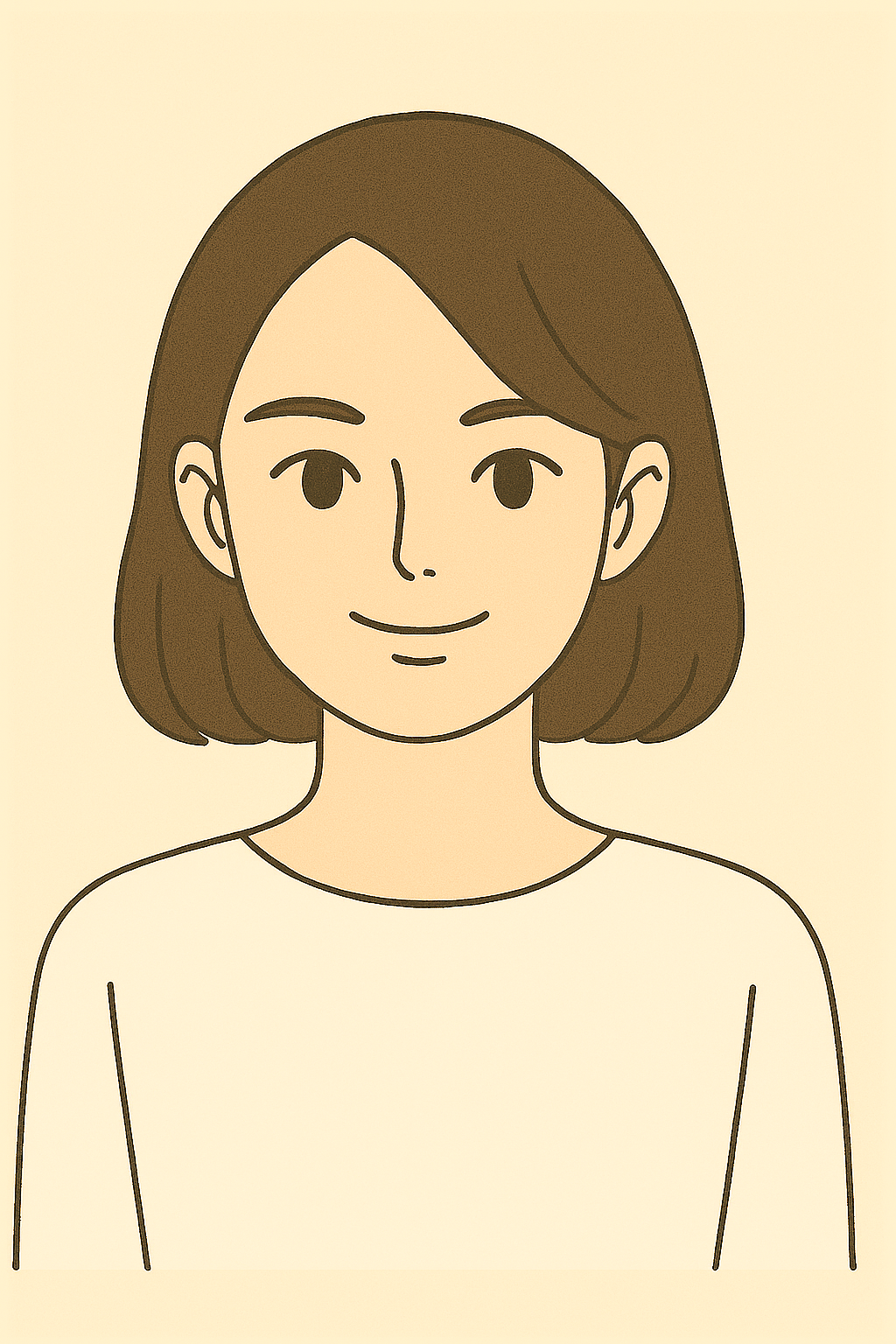
Aさん
前職より転職。通信大学で司書資格を取得。イギリス出張でオープンアクセス調査担当。
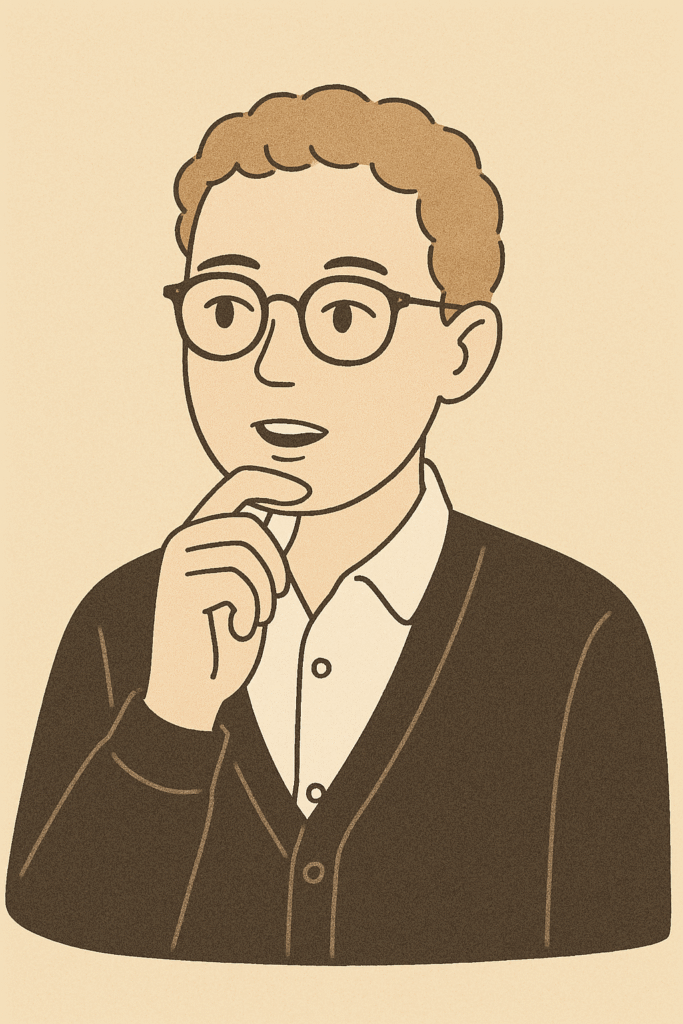
Bさん
前職より転職。司書資格なし。アメリカ出張経験あり。カウンター業務担当。
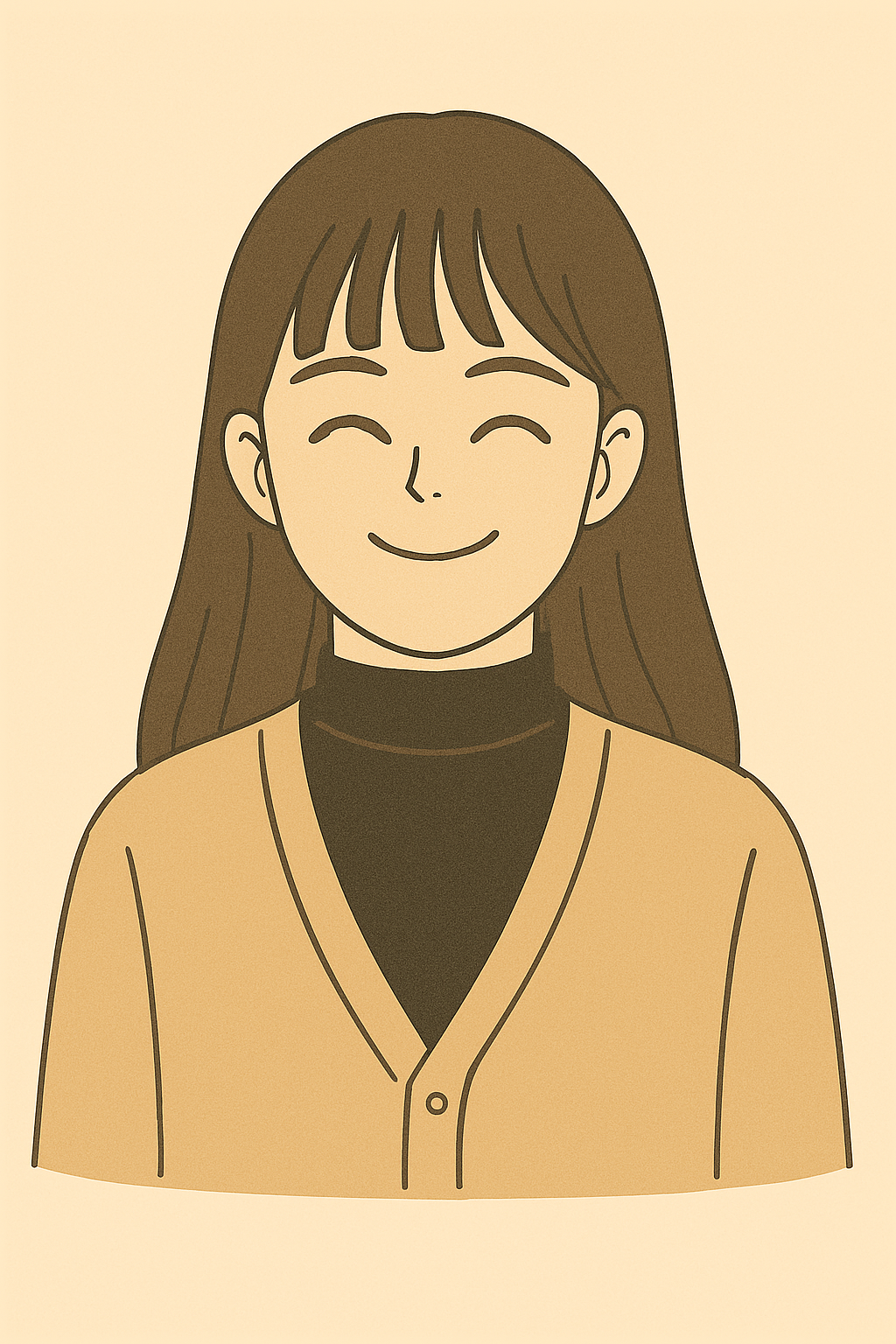
Cさん
年上の同僚に可愛がられている。小規模図書室勤務。受入から閲覧まで担当。
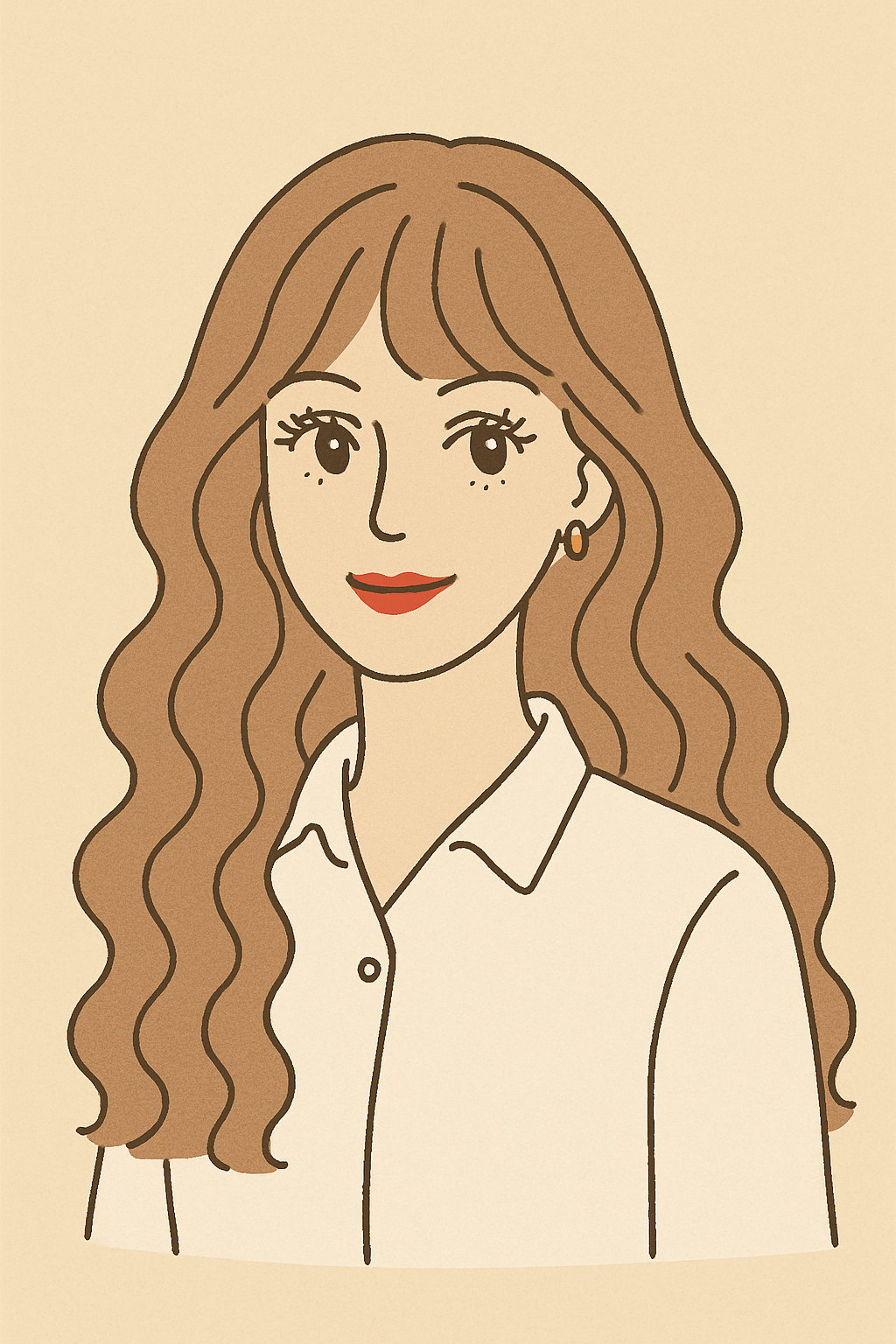
Dさん
前職より転職。
リポジトリ関連の部署に勤務。カウンター業務未経験。
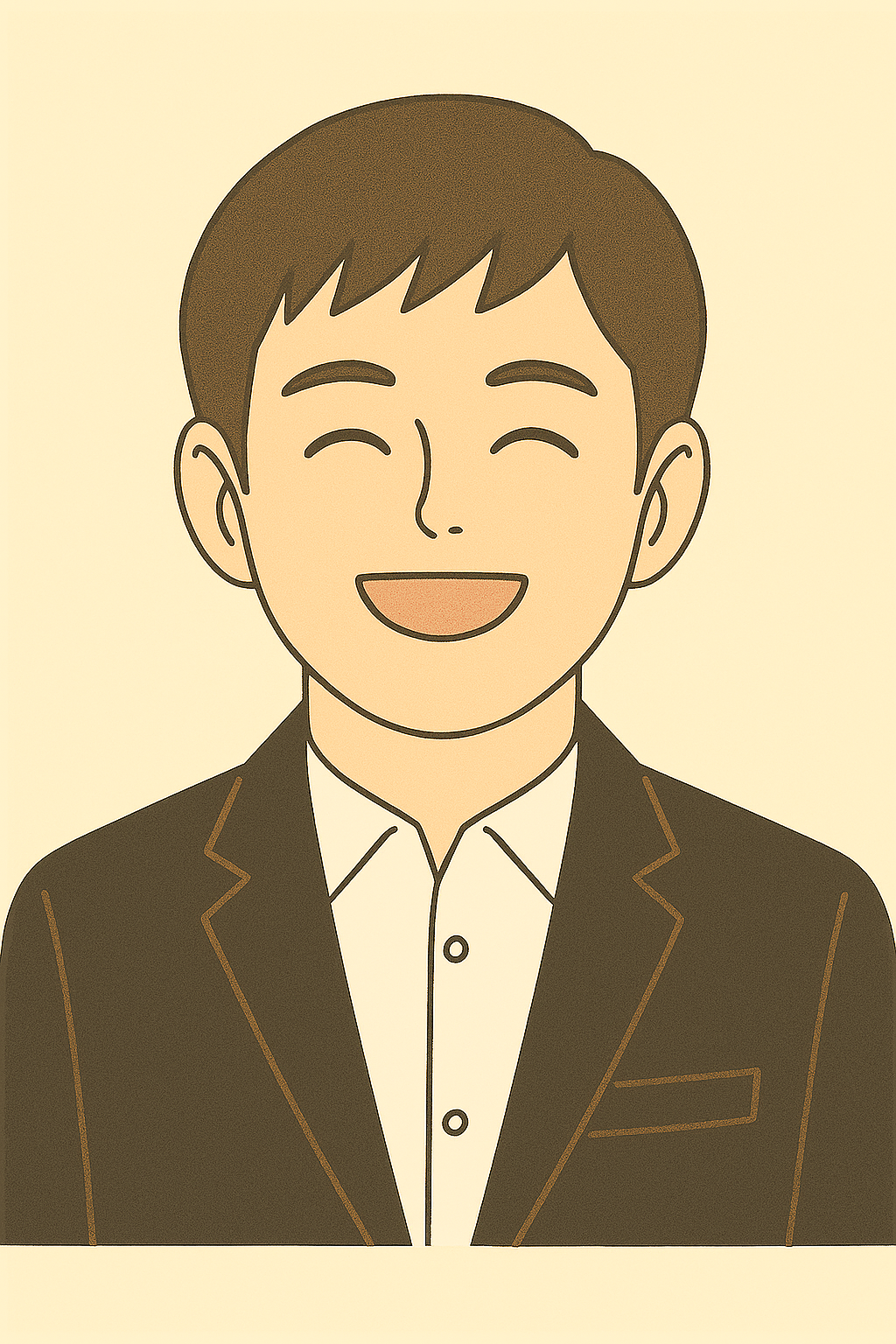
Eさん
以前からオープンアクセスに興味あり。現在目録担当の部署に勤務。
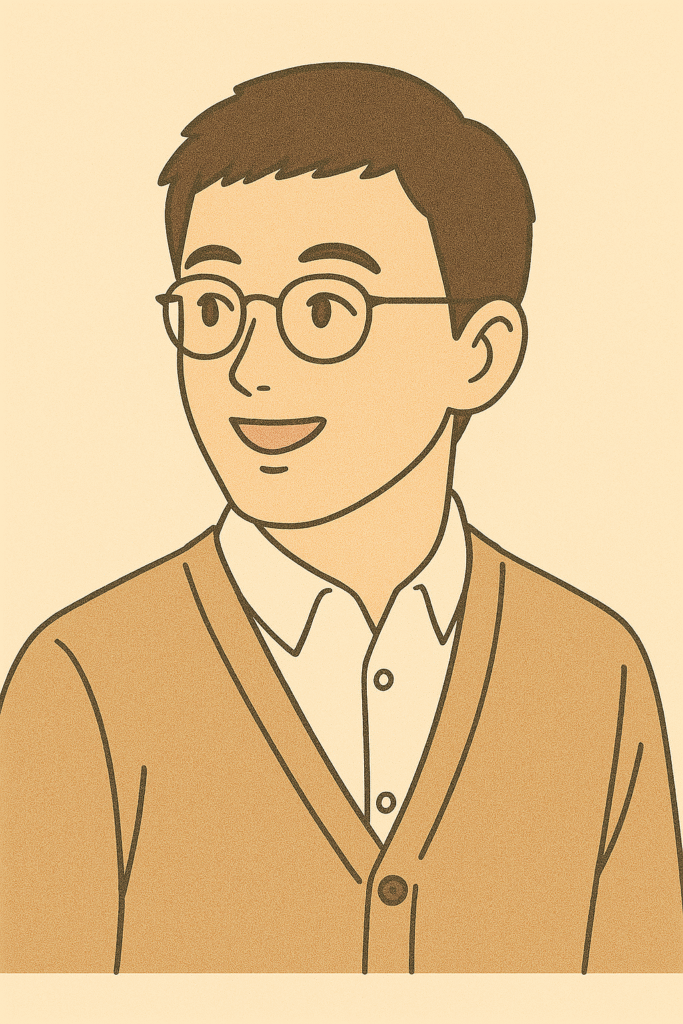
Fさん
前職より転職。小規模図書館でカウンターからリポジトリまで担当。前職在職中に、知識ゼロから学習をスタートして入職。
※参加者の情報は座談会開催(2025年3月17日)時点のものです。
※試験の形式や出題傾向などは座談会参加者が受験した当時のものです。年度により変更の可能性がありますのでご留意ください。
※似顔絵イラストは生成AIを用いて描いたものです。似ているかどうかは入職してからのお楽しみ♪
働き始めて、周りの人はどんな人が多いと感じる?
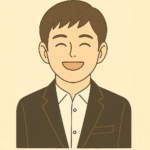
入職前は結構ステレオタイプな司書のイメージというか、メガネをかけている女性の方が多いのかなっていうイメージがありましたが、実際入ってみると、意外とそうでもありませんでした。必ずしもみんな「本が一番好きで」みたいな感じでもなくて、いろんな趣味を持っている人や様々なバックグラウンドがある人がいます。
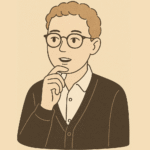
今おっしゃっていただいたことわかるなと思いました。「紙の本、命」みたいな人が多いのかなと思っていましたが、プログラミングとか、IT系に詳しい人が多いなっていうのは入職して思いました。実際に業務でもIT系の知識や、システム等を使うのでそこが一番びっくりしました。
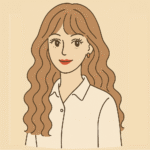
今まで皆さんが指摘された方向性とはちょっと違いますが、好奇心旺盛な人や、学ぶことが好きな人、学ぶことをやめないような方が多いのかなと思っています。直属の係長の方も15年くらいフランス語をずっと趣味でやっていらっしゃって。多趣味な方がいるのも魅力的なのかな。外部からは感じられなかった部分だなと思います。
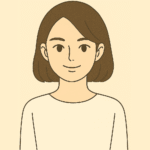
私もDさんのおっしゃっていることにすごく共感しています。今の係長が大学図書館研究会という研究会に所属していて、プライベートでもすごく図書館について勉強されてたり、すごく勉強熱心な方が多くて。私も入職して安心するのではなく、これからもずっと頑張り続けないとなっていうふうにすごく感じています。
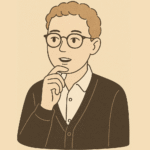
基本的に優しい人多いですよね。穏やかですごく面倒見がいい人が多いなって思います。
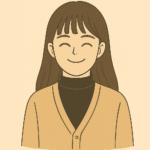
私の職場は自分と年齢が離れていて、ちょっとドキドキしたんですけど、みんな娘のように可愛がってくれて、楽しく働かせてもらっています。
働きやすさについてはどう感じる?
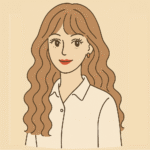
部署にもよるのだとは思うのですが、すごくお休みが取りやすいです。そういった福利厚生の面で言ったら、とても働きやすいと思います。私自身旅行が好きなのでお休みが取りやすいのは嬉しくて。ワークライフバランスが取れるような職場環境で、働きやすいんだろうなと思います。
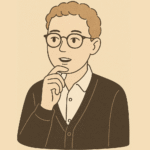
僕もそう思います。休みも実際取れるし、取りやすい雰囲気がある気がしますね。育児をされている女性も男性も普通に育児休業を取得しています。結構忙しめの部署の方でも、ちょっと夕方帰りますとか、普通に休暇を取っているのは意識が高いと思います。僕も1年目ですがわりと取っています。
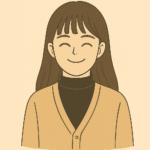
やっぱり上司の方がしっかり休暇を取得されているのを見ると、「じゃあ私も」って言えるので。みんながきちんと休んでいるところがいいとこかなと思います。
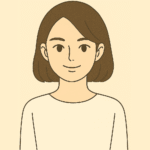
夏休みは前の職場だと連続で取れなかったのですが、今だと3日間まとまって長く取れるのはすごくありがたいと思いました。
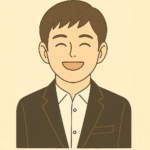
上の方から休暇を取得することを推奨されます。福利厚生に関しては本当に言うことないなっていう印象ですね。
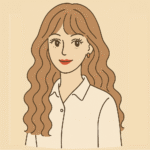
男性も育休を半年取ったりとかしていて、その面でもすごく先進的な部分があるんだな、そういう空気感なんだなっていうのも感じています。
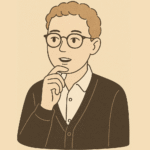
私の大学でも男性で普通に育休を取っている人がいますのでその辺は共通している雰囲気かもしれませんね。
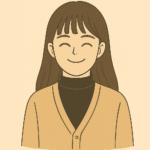
職場の雰囲気ですが少人数なこともあり、分からないことがあったらその場で相談することができます。すごく仕事を進めやすい環境かなと思います。
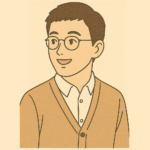
比較的皆さん雰囲気穏やかだし、基本的に真面目ですかね。前の職場に比べて、細かくルールが決まって、行動の規則が決められているのは、新人の僕としては、仕事がしやすく非常に助かっているかなと思います。
大学図書館や学術情報流通をめぐる諸問題の中で、今一番関心のあることは?
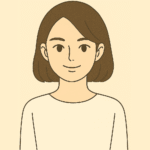
私からいいですか?つい最近、同期のBさんCさんもですが海外出張に行きました。私の担当はイギリスで各大学のオープンアクセスやスカラリーコミュニケーションを調査したのですがそれもあって、最近はオープンアクセスにすごく関心があります。
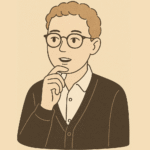
Aさんから話をいただきましたけど、私はアメリカのボストン、ハーバード、マサチューセッツ等の調査をしました。同じくオープンアクセスに興味があるのですが、入職前はあまり情報がなく、現在はリポジトリと関わりのないカウンター業務をしております。そのため、興味はあるけど、「どう勉強すればいいのか?」みたいな感じがもどかしいです。Dさんはリポジトリ関係の業務をされているとのことですがオープンアクセスも絡むのでしょうか。
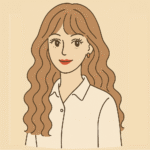
そうですね。もう思いっきりリポジトリ関連の業務なので。研修や講習会、係長に貸していただいた本等でオープンアクセスの情報を得ている感じです。
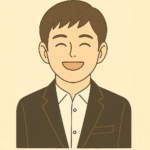
僕は入職前から割とオープンアクセスに興味がありました。在学中に論文を出させていただくことがありましたが、その時にAPCが20万円ぐらいかかったのが結構衝撃でした。そういうところから図書館の仕事に興味を持ったっていうのもあります。そのため、オープンアクセスに関する学内のワーキングに関われていることは、やりたいことができているので、すごく楽しんで仕事ができています。
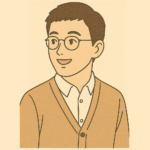
年々職員が少なくなっているという状況なので、カウンター業務の他にリポジトリ登録の作業も並行して行っており3月末は忙しい状況です。もっと正職員で働いている職員がいると、今できないこともできると言いますか。もちろんリポジトリ登録の加速化もですし、図書館のサービスの多様化も進めていけるかなと。
今困っていることはない?どんなことで困っている?
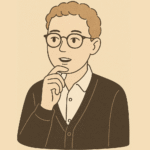
カウンターで利用者対応の業務をしているのですが、一方で図書の受け入れや登録といった目録系の仕事があるじゃないですか。登録して利用者に提供するのが一連の流れだと思いますが、その最初のところがわからないことを課題に感じています。隣の目録を担当する係を観察してこんな感じかなと思っていますが、本当にその辺の知識をどうつけていけばいいか。多分、実際そういう仕事しないとわからないんでしょうけど、今困っているって言ったらそのぐらいですかね。
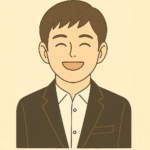
今、目録の仕事をしているのですが、逆にサービス系の仕事が全くわからない。その辺はもどかしいですが、まあ1年目だから仕方ないのかなとも思います。しかし、サービス系の仕事もやっぱり早く覚えたいなとは感じます。
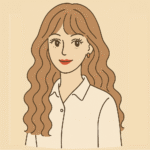
それで言ったら私はカウンターに1回も立ったことないです。裏方のデスクワークをずっとやっているので。困っていることと言ったら運動不足とか起きていますね。私の係はブックトラックすらなく、やっぱり本に囲まれて仕事をするんだと思って入職したのですが、本にほぼ1回も触ったことがないという。そういった仕事もあるよっていうのは、これから入職する皆さんには知っておいていただいたらいいかなって思います。
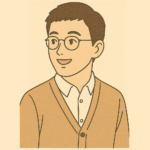
皆さんが話されていることを聞くと大規模図書館さんって結構仕事が完全に分けられているって感じですね。今、働いていて、ギャップがここであるんだなっていうのを非常に感じました。先ほども少し話しましたがカウンター業務とリポジトリ等の図書館のデータに関する業務を平行して行っています。他の大学図書館に比べてやっぱり規模が小さい分、皆で分担し合いながら様々な業務に実際に触れられて勉強しつつ仕事ができているのは自分にとっていいのかなと思います。
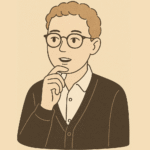
小規模な図書室が多くある大学も存在します。AさんやCさんが勤務している図書室だと閲覧系も収書系もやりつつみたいな感じだったりするのでしょうか。
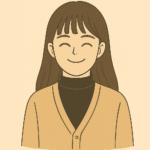
私の職場では内部にさらに小規模な図書室があります。私はそこを一人で担当しているため、その図書室については年間を通して閲覧でも受入でもだいたい自分が行わなければなりません。細々した業務がいっぱいあり、まだ覚えきれてない感じですが一通りの業務をやらせていただいたのはいい経験になりました。
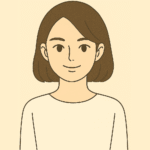
私も小規模な図書室で受け入れの業務を担当していますが、閲覧系の業務はまだやったことがなくて。次の職場に行った時や、他の全然違う業務をやる時に、ついていけるのかなとか、やったことないけど大丈夫かなっていうのが漠然とした不安で。やっぱり異動に関することが少し不安だなっていうのはちょっと感じています。
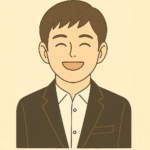
さっきのオープンアクセスの話に絡めると、勉強したいと思っても、なかなか体系的にまとまっている教科書がありません。雑誌『情報の科学と技術』にはオープンアクセス系の論文がよく出ているので、たまに確認するようにしていますが全体像がなかなか見えないので、勉強の仕方が難しいなというのが困っているところではあります。
採用試験どうだった?どんな対策をした?
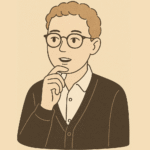
僕は前職があって働きながらだったため正直もう時間が全然なくて。とにかく最初の教養試験の点は取らなければと思い、とりあえずそれはもうとにかくやりました。あとは過去問とか見て英語が出るのは分かっていたので、TOEICの勉強も兼ねて英語を勉強しつつ。司書資格を持っていたので、その時の教材を引っ張り出してきて、一通りおさらいしたりとか。あと皆さんは『司書もん』という問題集があるのを知っていますか?それを一通りやったりしました。だけど思ったより司書資格のところよりも、今の学術情報の流れとか、その辺の方が出るじゃないですか。それを自分はほとんどやってなくて、とても後悔しています。
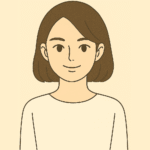
私も働きながら転職活動をしていました。司書資格を持っていなかったので、通信大学に入りながら勉強していたんですけどね。大学図書館の職員も司書資格が必要なのかなって思ったら、実はいらなくて。テストでも司書資格の勉強はそこまで出なかったので、教養試験対策とか、二次試験(専門試験)の対策とかに時間を割いても良かったのかなっていうのは少し思いました。
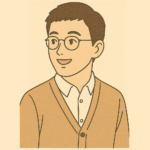
僕も前職があったので、仕事をしながら勉強をしました。もともと図書館の知識が全くないところからこの職種に就きたいと勉強し始めたので、Aさんと同じく通信で司書資格の勉強をしました。勉強のボリュームで言うと司書資格の勉強が8で、教養試験の勉強の方が2ぐらいのペースです。教養試験をクリアした後の専門試験の方は図書館の専門的な知識に関する出題がされるので、そこに関してはやっぱり司書の資格の勉強をしておいて良かったと非常に感じています。募集項目には司書資格は書いてないですが、図書館に関する知識がないと、やはり筆記はできないので、僕としてはやっておいてよかったなって非常に思っています。
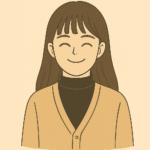
私は結構教養試験ができなくて。もう大学入試以来の算数と英語でしたが、出題の割合が大きいのは決まっているのでひたすらやって。なんとかパスしたとわかった瞬間に二次試験(専門試験)の勉強を始めたのですが過去問を見ていたら、やっぱりBさんがおっしゃっていたみたいに、最近の学術流通のこととか多くて何を勉強したらいいかわかりませんでした。先輩と話す機会があり相談してみたら、『学術出版の来た道』という本に結構この試験の答えになるようなことが載っているよっていうのを教えてもらって。それとにらめっこしながらずっと勉強をしていました。
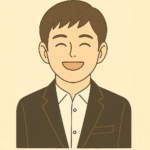
これから専門試験を受けられる人向けに言えることがあるとしたら、専門試験は択一式で問題数もそれほど多くないのでそんなに差がつく試験じゃないということです。簡単な問題をとにかく落とさないことが大事な試験だなって受けている時にすごく思いました。難しい問題を頑張るのもすごい大事なんですけど。とにかく基礎的でみんな正解できる問題を絶対に正解できるような勉強が大事になるのかなと試験で思いましたね。
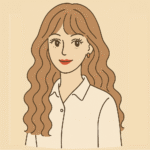
皆さんがその筆記試験の話をしてくださったので機関訪問とか面接のことで言うと、それぞれの大学や図書館の特色をきちんと調べるのが大事かなと思います。調べた上で、自分がやりたいことと合致させるような志望動機が言えるようにする。あと、公務員試験の就活本みたいのをよく読んだことが割と役に立ったかなって思います。ゼロベースでやるより参考になるものがあったら、なんでも読んでみたりするのはいいかなと思います。
大学図書館職員としてやってみたいこと・頑張りたいことなど今後の目標
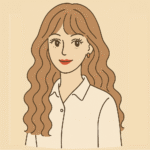
本日お話ししたみたいにオープンアクセスの業務をしているのですがやっぱり図書館に来たからにはサービスの仕事をやりたいなという気持ちはあります。今、裏方の仕事なので、利用していただいている方の顔が全く見えないっていうのは、ちょっと残念だなって思うことがあるので、利用者さんの声を聞きながらお仕事をしてみたいです。勤務先に、公共図書館と大学図書館が一体となった国内でも珍しい取り組みがあります。そういったものの後押しじゃないですが、大学の知や専門的な情報を、学内だけじゃなくて地域一般の人たちに流通させるっていうようなことをやってみたいと思っています。
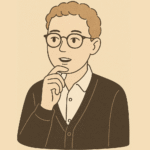
真逆になりますがそのリポジトリとか、オープンアクセスとか、これから図書館、学術流通の中で多分大事にコアになっていくところを本当にほとんど知らないので、そのあたり勉強していきたいです。そうして知識をつけて引っ張っていくって言ったらおこがましいですけど、ちょっとでもそれらに道筋をつけられるような図書館員になりたいなというふうに思っています。
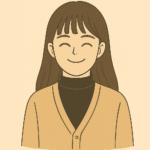
私はこの1年やってみて、いまだに右も左もわからなくて。海外出張行った時も一緒にいた上司や先生に大いに助けていただいて、どういうふうになりたいとかもわかってないんですけど、これからいろんな部署とか仕事を行っていき、何か自分の得意なことやエキスパートになれることを見つけて、それが無理でも逆にオールラウンダーで何でもできる人になるとか。まだまだ途中なのですが見つけていけたらなと思っています。
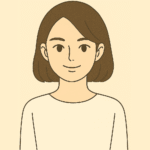
私も今回海外出張に行って、これからも業務外でも英語の勉強とかしっかり頑張りたいと思いました。それこそカウンターとかで、英語で対応しなければいけない時に、すぐに対応できるような職員にはなっていきたいなっていうふうに思っています。
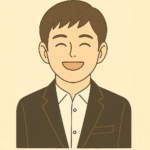
「自分が学生時代にこういうサービスがあったらよかったな」みたいな部分が何個かあります。そういうところを今の学生さんたちに還元できるように、自分がしてほしかったことを提供できるような司書になれればいいかなっていうふうに思っています。
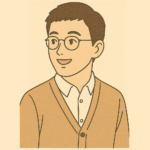
皆さんもおっしゃるように英語の勉強を進めなければならないと思います。勤務先は実際に外国人の研究者の方をメインに図書館のサービス提供をしているということもあって、外国から来た研究員に英語で対応しないといけない場面が多く、日々勉強していかなければいけないなと思います。またうちの係長が1年に2回ほど、欧州の研究協会やアメリカで開催される図書館協会において英語で発表しており、将来的には僕自身もそこで発表しないといけない立場になるのかなと思うので、今から英語を勉強していかなきゃいけないと思っております。
座談会はこれで終了です!
ここまで読んでくださった皆様、参加してくださった1年目職員のみなさん、ありがとうございました!