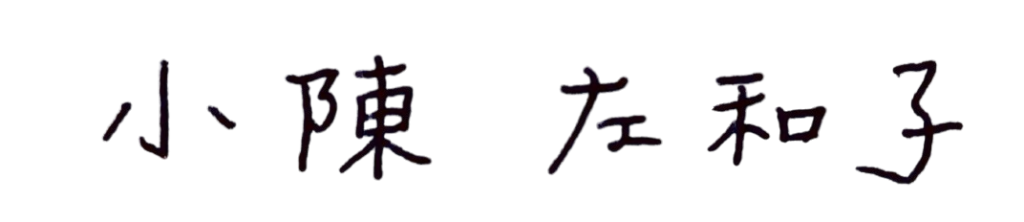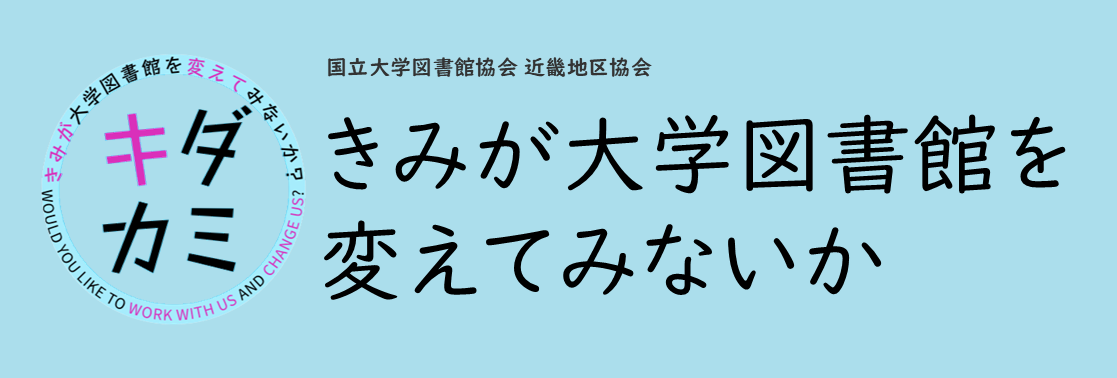エグゼクティブのつぶやき vol.1

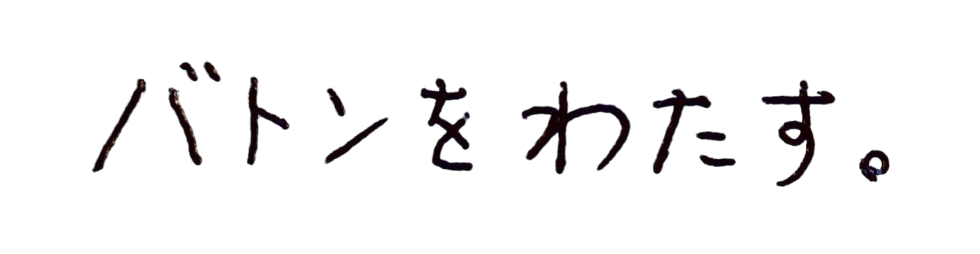
16年前に国立大学図書館の管理職となり、数年おきに組織を異動する立場となりました。ひとつの処にとどまれない寂しさももちろんありましたが、それぞれの場所でたくさんの人と出会い、共に働けた喜びの方が上回っています。
これまで、何人もの人に「どうして管理職になったんですか? しんどそうなのに」「管理職って何が楽しいんですか?」と尋ねられました。
私は自分から手を挙げたわけではなく、どちらかというと有無を言わさず、のような成り行きではありました。また、私が新人の頃は、国立大学図書館に女性の管理職は皆無に等しかったということもあり、自分のキャリアプランの中に(そもそも当時そんなものを考えていたかすら、今となっては怪しいですが)、その選択肢は想定もしていなかったように思います。
しかし、管理職になってみて思ったのは、これは、先達から受け取った、目に見えないバトンを渡す「恩送り」なのだということでした。勤め始めた頃から、数知れない先輩の方々に育てられ、若輩者のわがままを聞いていただき、時には反発する失礼な態度も大きな心で受け止めてくださり、思ってもみなかった経験をさせてもらえたからこそ、今の私があると思っています。それを今度は後輩のみなさんに受け継いでいくこと、経験・知見を伝えていくことが自分の役目なのだと悟りました。
組織の中では、そういったマネジメントを担う人だけでなく、ひとつのことにじっくり取り組むスペシャリスト的役割ももちろん必要で、多様な選択肢が用意されるべきです。図書館職員を志した若かりし頃の私も、カタロギングを究めたい!などと夢見たりしていました。課長になれと上司に言われて「いやですぅ〜私には無理ですぅ〜」と逃げ回りもしました。しかし、いざその役目に就いてみると、大事だと思うことを様々なステークホルダーへ自分の言葉で語ることができ、組織がやるべきこと、やりたいことに、より深くコミットできる立場であることに喜びを感じるようになっていました。また、自分が採用に関わったり、一緒に働く中で意見をたたかわせたり鼓舞したりした職員が、たくましくなって伸び伸びと躍動する姿を見ることができるのも大きな役得のひとつです。そして、自分も少しは成長できたのかもしれないと思えるようにもなりました。
逆に、管理職になって辛かったことというのはほとんど覚えておらず、もしあったとしてもおそらく、その時々で周りの人々が助けてくれたり、共に闘ったり、一緒にお酒を飲んで愚痴を聞いてくれたり、という良き思い出に上書きされてしまったのだと思います。「長」と肩書きが付いたところで、所詮独りで考えて判断できることなど限られているので、よくよく人と対話することが何よりも大事だということも学びました。
もちろん、すべての職員のみなさんに管理職の道を勧めたいというわけではなく、それぞれの立ち位置で活躍できるのが一番だと思っていますが、こんな選択肢もあるんだよ、ということは心に留めておいてもらえるとうれしいです。きっと、新しい景色が見えるはずです。
まあ、社会環境も人事制度も変わり得るものですし、昭和の時代が終わる頃に採用されて間もなく定年を迎える私などが辿ってきた道よりも、必ずや明るく輝かしい未来が開けるはずだと信じています。どうかみなさん、仕事を、人生を楽しんでください。
大阪大学附属図書館 事務部長